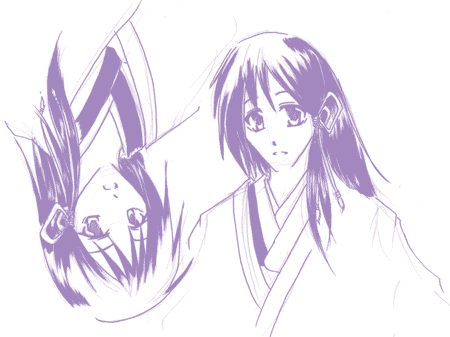背景の元絵
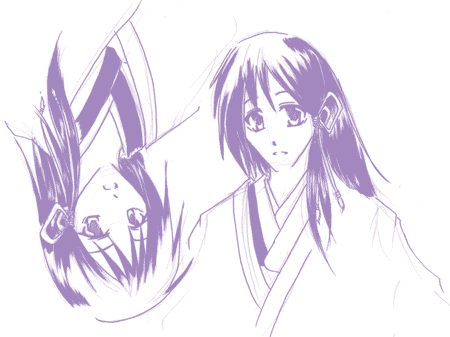
母はよく言い聞かせるように言った
「強くおありなさい 優しくおありなさい」
私が五つになった頃 母は亡くなった
生来体が弱かった母は 私達を産んだ頃から容態が悪化した
―双子は忌み子
よく 言われた
双子の姉である伊勢(いせ)が産まれ 私が産まれた時 不吉だからと
すぐに殺められようとしたのを助けてくれたのは 腹違いの兄の母だった
男子を二人産み 各地へ有数の繋がりを持つその人の発言力は強かった
仲のよかったその人は母のお産に立会い 産まれた私を母に抱かせて周りに言った
「懸命に産まれてきたこの子を 殺めるのか?」 と
それでも向けられる目は冷たかった
事あるごとに投げつけられる言葉は辛く悲しいものばかりだった
唯一の逃げ場は母の元だった
そこしか居場所がなかった
そんなある日 ”あの人”が来た
記憶している中でも それが一番初め
私は確か三つで ”あの人”は八つだった
「あなたのお兄さんよ」
母の 柔らかい声で告げられ ”兄”は頭を下げた
その後ろには よく会いに来てくれる女の人
母が言うにはその人の子供だという
「お父さんは一緒だよ」
人懐っこい笑顔でその人は言う
姉である伊勢は習い事というのでいない
正直 怖かった
今まで会った人全てに投げられた冷たい言葉がよみがえる
―ヒトに会いたくない
それがあの頃の私だった
嫌で嫌で仕方なくて 母の影に隠れてこっそりと”兄”を見ていた
「妹?」
「そうだよ」
初めて私を見る”兄”
物珍しげな視線が投げかけられる
嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ…
近づいてくるのがわかって ぎゅっと目を閉じて 母の着物を握り締めていた
ぽふん
想像していたもの 全てを振り払うかのような 出来事だった
頭に軽い衝撃と あたたかさ
驚いて目を明けて見ると 少し照れている”兄”がいた
「…ちいさい」
頭を撫でながら ”兄”は呟いた
「そりゃあ 三つだからねぇ 九つのあんたよりでかかったらヤでしょ」
「うん」
そう言って ほんのりと笑った
母や伊勢 そして よく来てくれている女の人―しきさん―以外に あたたかかった人がいなくて
始めてその人を”兄”なのだと 確信した
「お…にーちゃん?」
ポツリと呟かれた言葉に 自分でも驚いた
「うん」
兄の手は大きくて あたたかかった
それから二年程経って 母は亡くなった
幼い私たちの引取り人は しきさんになっていた
伊勢だけを引き取る という話は多数出ていたけれど 二人揃って という話はしきさんだけだった
その時上の兄は十一で 下の兄は九つだった
風当たりはよくなかった
それでも しきさんと兄達は変わらず接してくれた
それだけが支えだった
伊勢にも迷惑をかけているし 兄達にも迷惑をかけているとずっとずっと思っていた
何かよくない事が起きれば 皆口を揃えて「忌み子が」と蔑んだ
その度に どうしていいかわからず 私は泣いていた
向けられる感情が冷たいほど 苦しいほどに伝わってきたから
どうしていいかわからず 私は泣いていた
伊勢はその度に言い返した 私が悪くないと 忌み子など関係ないと
下の兄は私が泣き止むまで ずっとあやしてくれていた 上の兄も
ただ 兄達は何も言い返さなかった
それを伊勢が尋ねたことがある
「どうして おにーちゃん達は言い返さないの?」
下の兄が苦笑しながら答えた
「俺はまだ うまく表現できないんだ」
上の兄は 静かに答えた
「まだ 黙らせる程の術を持っていない」
二人の兄の返答に 伊勢と二人して首をかしげた事がある
そんな頃から 上の兄は毎日決まった時間にどこかへ行っていた
帰ってくるときはボロボロになっていた
「どこに行ってるの?」
「稽古だよ」
そういって撫でてくれる兄の手は あの頃よりもちょっとごつごつしていた
上の兄は時折 数日間出かける事が多くなっていた
伊勢が習い事でいないとき 私は下の兄と一緒にいた
下の兄の傍らには ”誰か”がいるのが あの頃からぼんやりとわかった
気になって気になって ある日下の兄に尋ねたことがある
「おにーちゃんの 傍にいるのは 誰?」
不安で怖くてびくびくしながら答えを待っていると
ちょっと驚いた顔をして ちょっと嬉しそうな顔をして頭を撫でられた
「友達だよ」
産まれたときから ずっと一緒にいる
私にはぼんやりとしか見えないけれど 兄にははっきりとその姿が見えている
ちょっと 羨ましかった
人形程の大きさのお友達は 兄の頭の上や肩に乗っていた
いいな と思わず言ってしまった
「和泉(いずみ)にもいるだろう?伊勢が」
「でも 伊勢は今いないし…」
「伊勢が言ってたぞ 和泉は私の自慢の妹なんだって」
「ほんと?」
「嘘は 言わない そう約束しただろう?和泉」
下の兄は よく本を読んでいた
たまに覗いてみるが よくわからなかった
兄も まだあまりよくわからないと 苦笑して言った
それでも兄は読んでいた これから必要な事だからと
私も一緒になって読んでみたけど わからなかった
ちょっと遊ぼう と兄が折り紙で鶴を折ってくれた
私も一緒に折った
出来上がった二羽の折り鶴を 兄は両手に持って小さく何か呟くとその手を離した
落ちると思っていた鶴は そのまま浮いて部屋の中を思うままに羽ばたいていた
「あれだけ読んで これぐらいしかまだ出来ないけど」
「ううん すごいよ!おにーちゃんはすごいよ!」
あれから三年経って 今度はしきさんが亡くなった
「後見人になった」
十四になった上の兄が 静かに 強く言った
ばらばらにならなくても済む という意味だと後から知った
母が死んだ時のように 誰が引き取るという話が持ち上がったらしい
それを 上の兄が一掃した
いつの間にか上の兄は しきさんと同じぐらいの発言力を持っていた
そこまでの発言力を持つまで 無理をしながら 必死になっていたらしい
それを聞いたのは 上の兄が旅立つ数日前だった
「ごめんなさい」
旅支度をしている上の兄の部屋の前で 私は俯いたまま 兄の顔を見ることすら出来ずに佇んでいた
いなくなる前に 旅に出てしまう前に 謝らなければならないと思ったから
兄が 部屋に入るよう促しても 足が前に出なかった
入ってはいけないように 思えた
「ごめんなさい ごめんなさい」
「和泉 なにを謝る?」
「私のせいで 私がいたから 兄さん達に 迷惑かけた」
ぽろぽろと涙が溢れてきても どう止めればいいのかわからなかった
私という忌み子がいなければ母も責められることがなかった
私という忌み子がいなければ伊勢も自由に出来たのに
私がいたから しきさんや兄達にも迷惑をかけてしまった
「和泉は悪くない」
「でも わたしは」
「関係ない」
目線を合わるように しゃがんだ兄は あの頃と変わらず 頭を撫でてくれた
「和泉は俺の妹だ 俺は和泉の兄 兄なら妹を守るのは当たり前だろう?」
だから気にしなくていい
うっすらと 感情を表すのが苦手な兄が笑顔で言ってくれた
あの頃と変わらない あたたかさがあった
「ごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい」
「和泉は謝ってばかりだな」
嗚咽が漏れる
兄の腕の中は 居心地がよくて いなくなるのが実感できてしまって
急に寂しくなって
「大丈夫 ちゃんと 帰ってくるよ」
兄が嘘を言う人じゃないのは よく知っている
約束も守ってくれる事も よく知っている
それでも それでも もしかしたら帰ってこないのかもしれない
もう 会えないのかもしれない
そんな事ばかりが 頭の中を埋め尽くしていて
何も言わなくても 兄達はどこか直感的なもので感じ取っていたのかもしれない
「死なない ちゃんと ここへ帰ってくる」
兄が十五で 私はまだ九つだった
わがままだと思う でも 兄に行って欲しくなかった
その旅が 大事な大事なものだとわかっていたのに
「手紙を 書く 式で飛ばせば どこからでも 届くから」
「お返事…出せない」
「朔か巽に言え そうすれば飛ばしてくれる」
あの二人には伝えておくから
最後の最後まで 気を使わせてしまった事に罪悪感が募る
それなのに どこか嬉しいと思っている自分がいる
なんでなのかわからずに ただその感情が不思議だった
「帰ってくる頃には 今よりも謝る回数が減ってればいいな」
「どうして?」
「言っただろう?和泉は悪くない 悪くないのに 謝ってばかりだ」
「だってそれは…」
「気にしなくていいんだ 何も 詫びることも謝ることもない」
そう言って微笑んだ兄の顔は 今でも鮮明に覚えている
数日後に 上の兄は旅立った
「ぼんやりとしてるね 和泉」
空を眺めていたら声をかけられた
人形ほどの大きさの”彼”は 今では私の話し相手でもある
「きおう 兄さんに言われたの 私は謝りすぎだって」
欄干にもたれていると 隣にきおうが腰を下ろした
私を見ながら きおうは言った
「んー 確かに和泉は謝りすぎだよ?」
「そう かな」
「ジンも気にしてたぞ 和泉はもっと自由に振舞ってもいいのにって」
「兄さんが?」
「うん 伊勢と同じ事してもいいのにって」
「いいの 伊勢がいろいろ教えてくれるから いいの」
まったく知らない誰かから教わるよりは 伊勢から教わった方が何倍もよかった
それに 私に教える事で 伊勢自身の復習にもなるようだ
おかげで今では琴に三味線に生け花に 一通りは出来るようになってきた
「でもジンに合わせる様に本読んでるでしょ?」
「ううん ただ単に私が読みたいだけよ」
「そうなの?」
「うん それにこの前ね 朔(さく)さんに褒められたの」
朔さんは陰陽寮の中でもずば抜けて実力のある人だった
それでいて 上の兄と仲のいい人なので時間があいた時には 顔を見せに来てくれるし会いに行く
よく一緒にいる巽(たつみ)さんもだ
二人揃って 出世頭だとか言われているのを 小耳に挟んだ
「なかなか筋がいいって」
「うん 僕もそう思う」
「そうかな?でもジン兄さんにはまだまだ」
「ジンだって見習いだよ 和泉が追いつけば…ジンも躍起になるかも」
「それは困る」
思わず声のした方に向く
ちょっと困ったような顔をした 兄がそこに立っていた
静かに歩み寄ってきて 腰を下ろす
最近 ジン兄さんは上の兄に似てきたなと 思う
顔とか雰囲気とか
そう思いながら眺めていると 目が合った
「何かついてるか?」
そう言いながらジン兄さんは 私の頭を撫でる
上の兄といい 私はよく撫でられるようになっている気がする
「覚えてるか?昔 和泉が大泣きした時に」
「え あ い いつ?」
ジン兄さんの目元が柔らかくなったのに 撫でられながら気付いた
「俺と兄さんと伊勢がいた」
「いつもいた」
「いつものように”ごめんなさい”って和泉が謝って泣いてた」
「…うん」
「そん時だな どうしておにーちゃん達は笑えるの?って」
幾人かいた 兄達としきさんを快く思っていない人達
その人達は私に向けた言葉や感情と同じものを 兄やしきさんに向けた
それでも しきさんは笑っていた 兄達は気にすることなど なかった
思い出した?と聞かれて コクリと頷く
「母さんは強かった 笑えることがどんな事なのか よくわかってたんだ」
「じゃあ 兄さんは?」
「強く なれたかもしれない」
「どうして?」
「だって 和泉に謝られても 笑って”違うよ”って 言える様になっただろう?」
ゆるやかに頭を撫でながら ジン兄さんは笑顔を浮かべて言った
不器用なのは知っている きおうからも聞いたから
それでも 笑顔を向けてくれるのは どうしてなのかわからなくて
「ジン兄さんは どうして笑えるの?」
「だって 和泉が悪いわけじゃないし 俺は 和泉には笑ってて欲しいから」
兄さんもそう思ってるんだよ
旅に出た兄は 帰ってくるまでに謝る回数が減ってればいいと言っていた
そういう 意味だったんだろうか
「兄さん」
「ん」
「ごめんね」
「いい いいから 兄さんが帰ってきたら笑顔で な」
「うん」
手紙に書こうと思う
『私は今日 始めて笑う意味がわかりました』 と
09.詫びても詫びても彼らは笑ってばかりで
→戻る
背景の元絵