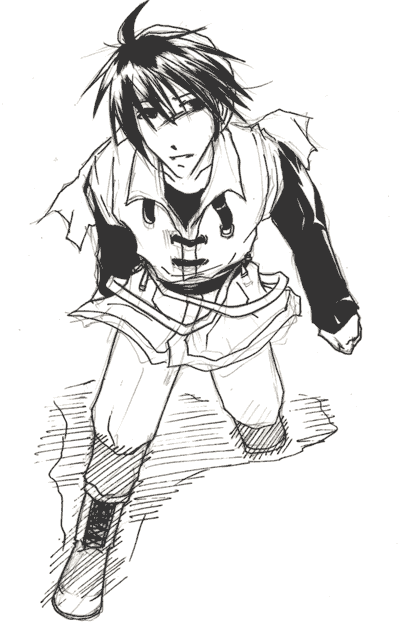背景の元絵
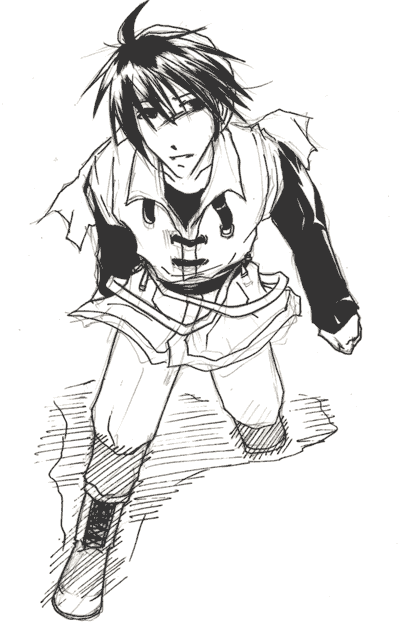
港町独特の 磯の香りが鼻をつく
眼前に広がる大海に 何となしに目を向けた
青一色とは言いがたい 紺碧が永遠に広がっているかのように思える
カモメの鳴く声で我に返り 足早に宿へと戻る
両手を塞いでいるのは これから必要であろう品々
一歩進むごとに紙袋と中身の擦れる音がする
(早く帰らなければあの二人がうるさかったんだ)
石畳の道をかけていき 数日間滞在する宿へと向かう
若年だけの旅人は珍しいのか 宿屋の主が色々と情報をくれた
何を買うにはどこの店がいい あそこは危ないから気をつけろ…などなど
それらの情報を踏まえつつ ほかの店も見て周ったが 宿屋の主が言ったとおりだった
買出しをする際に 随分と役立つ情報をくれた主には感謝しなければ
宿屋の敷居を跨げば 主がこちらに気付き笑みを浮かべる
「おかえり 買出しはどうだった?」
「おじさんが言った通りだったよ すごく助かった」
ありがとう・と付け加えて 部屋へ戻る
階段を上り 部屋のドアを軽くノックすれば ドアが開く
「おかえり 夜志露」
「遅い やしろ」
十かそこそこの双子が顔を出す
後者の言葉に軽くため息をつきつつ 部屋に入る
抱えていた紙袋を渡し ベッドへと腰を下ろす
隣のベットでは 双子が中身を確認するかのように紙袋から出していた
気分としてはそのままベットに倒れこみたいが 出来ない
目利きである双子の意見を聞かなくてはならないのだ
これは あの頃からの恒例である
「うん 今回はいいもの買ってきたね」
男の子であるフィンドが笑顔で言う
それを見ると自身の目利きも上がってきたのだろうと思うが
「でもまだまだね!やしろ!」
手厳しいのは女の子であるティクトの方だ
彼女の希望であったリンゴに多少不満があるのか 未だに視線を注いでいる
外見は似ているのに こうも性格が違うとなると なんだか調子が狂ってくる
一体 どういう態度で接すればいいのか わからなくなってしまう
「そうそう」
急にがらりと空気が変わる
それは例えるなら いきなり海へと放り出されたかのような感覚
部屋の中だけに それは広がる
不可侵の領域 神聖なる雰囲気
絶対なる存在感を携えて 双子の纏う空気は急変する
それはすなわち「連絡」があるという事
「彼とは目的地が同じようだ」
「闇へと傾く彼を止めるか 消すか 早く決めなさい」
「「それが貴方の背負うもの」」
リンとした声が耳へと届く
何度目かの「連絡」は これからも慣れそうに無い
この独特の雰囲気が駄目だと 毎回認識しなおす
虚ろでありながらも その瞳は己を外すことなく じっと捕らえている
こちらが気落ちしそうなぐらいの気迫すら感じる
「…わかってる」
ようやく出せたのはたった一言
初めは声すら出せずにいたものだ
それに比べれば きっと成長していると思う
ふっと 憑き物が落ちたかのように双子の体から一瞬力が抜ける
それを見て ようやく肩の力が抜ける
「連絡」の終わった合図
「やしろ もうちょっと気の利いた言葉はなかったの?」
「あれは短すぎるよ」
いつもの双子
苦笑しつつも相手をしていれば それが日常だった頃を思い出す
あの 唯一人らしい生活を送っていたあの頃を
忘れたことは無い 不意に思い出すのだ
買出しをしている時 宿へ帰ってきた時 出迎えられた時
もう一人 いないだけなのに
「やしろ 聞いてる?!」
ティクトの声で我に返る
どうやら「連絡」の際 随分と時間が経ってしまっていたのか
窓の外は 真っ暗になっていた
街道に沿って 明かりが点いているのが窓越しにわかる
空は 暗い中に 月がぽっかりと浮かんでいた
「……寝よう」
ごめんごめんとティクトをあやしながら ベッドに向かう
ファンドとティクトは同じベッドで 寄り添うようにして寝る
あの頃と変わらない光景
もうすぐ あの 儚い笑みを浮かべる彼女が階段を上がってくる
それで申し訳なさそうに笑う
ボロボロの己を看病して さらには居候させてくれたのは他ならぬ彼女なのに
彼女はいつも申し訳なさそうだった
今まで感じた事のない安心感と安堵感が彼女の傍にあった
柔らかい声で呼ばれる度に―
「 夜 志 露 」
ふわりと また空気が変わった
「連絡」以外での 感覚は久しぶりだった
ゆっくりと声のした後ろへと 体を向ける
暗い闇にぼんやりと 白く光る何かが視界の隅に映った
早くなる鼓動を無理やり落ち着かせて 逸る気持ちを落ち着かせて 振り返る
「 と き お 」
ゆるやかな風を纏った彼女が そこへ佇んでいた
あの頃と一寸も変わることの無い彼女
己の記憶力もたいしたものだ・と 自負しつつ彼女と向き合う
白く柔らかく光る彼女は 床に足をつけることなく そこにいた
背中あたりまである髪が ゆるくなびく
「連絡を 聞いた?」
儚く微笑みながら 彼女は言う
「聞いた」
自然と 握っていた手にさらに力が入る
気を抜けば彼女に全て持っていかれそうだ
「彼を 討つの? それとも」
「季緒 殺すのは最後の 本当に最後の最後で何も打つ手が無くなってからだ」
「助けるの?」
「出来るなら俺は助けたい」
「闇は彼を手放さないわ 随分前から彼を狙っていたみたいだから」
「イレイザーは消す者だ 闇も 消せるかもしれない」
季緒が 静かに目を閉じる
「触れていい?」
人の温もりを教えてくれたのは彼
失った温もりを再び与えてくれたのは彼女
忘れていた温もりを 繋ぎとめてくれているのは ファンドとティクトの二人
イレイザーとして 消していた頃の記憶は断片的にしか無い
幾人かの イレイザーと呼ばれていたメンバーは かろうじて覚えている
その中でも 彼は格別だったはずだ
二十歳そこそこの歳で イレイザーのトップにいた 彼
その彼が イレイザーという組織を壊滅させたのは そう遠くない昔
もともと人数は少なかったし 少数精鋭というやつなのか
他のメンバーは 生きているのかどうかもわからない状況
ただ 目にしたのは 折り重なる屍の上に静かに佇んでいた彼
纏うことのない 闇を纏った彼が その瞳で己を見下ろしていた
折り重なっていた屍は 組織の幹部達面々だったような気もする
血溜りは人数の割りに少なく 局部ごとに「消されて」いたのかもしれない
ゆっくりと彼が口を開き 紡いだ言葉は彼の声ではなかった
それ以降の記憶は無い
ただ 気付いたら季緒に拾われて 双子達と一緒に生活していた
「季緒 俺が死んだら 連れて行くか?」
「どうして?」
ひとは温かいと 思う
例え 目の前にいる彼女が人という区分に分けられない存在だとしても
「空は望んでいるのだろう? 戦う者が増える事を」
手に手を添える様な形になる
さらさらと 季緒の髪が手を滑っていくのが くすぐったいようで心地いい
あの頃がずっと続いていくものだと思っていたのに
脆くも崩れ去った 平穏な 温かい日々
「神は信じないって 夜志露言ったじゃない」
「あの双子と一緒にいるんだ 今更そんな事は言えない」
「じゃあ 信じてるの?」
「神は―」
神という概念はいつの間にか己の中にあったのだ
ただ 神に祈る という行為を周りの人に比べでほとんどしなかっただけで
「自ら望んで 干渉するものじゃあ ないだろう?」
そう言っえば 季緒が儚く微笑んだ
「東の国の "彼ら"のような考えね」
「俺はもともと 東の国出身らしいからな」
よく覚えてないけど
黒目に黒髪という外見だけで 東の人だと周りには言われた
それが東の国の特徴だとも
彼も 確か東の国出身だったと言っていた気がする
「死なないでね 夜志露」
「わかってる」
「私は 出来るなら貴方を迎えに行きたくないから」
そう言って 彼女は徐々に透けていき 消えた
彼女の名残だけが手に残った
「いいと思うよ」
不意に掛けられた声に 必要以上に反応してしまった
勢いよく 振り返れば上半身を起こしているファンドがいた
「僕は 夜志露の考え方は好きだ」
「…ありがとう」
「ちゃんと寝るんだよ?」
「ファンド 俺はもう18だぞ?」
「ティクトが起きてたらまだ酷いからね わかってる?」
そう促されれば従わないわけには いかない
ファンドよりもティクトの方が 痛いところを確実に遠慮なくついてくる
だったらおとなしく ファンドの言うことに従っていた方がましだ
ベッドにもぐり おやすみと声をかければファンドは納得したように頷いた
そういえば 船が出るのは 明後日だったな
気付けば意識を手放していた
特に何事も無く数日を過ごした
そして今日は 船の出る日
一週間前に買ったチケットがようやく役に立つ日でもある
生まれ故郷かもしれない 東の国へと向かう船へ乗る日
荷物をまとめ 宿を後にして港へと三人で向かう
港には大小さまざまな船が その帆を降ろし また上げていた
「どれに乗るの?」
ティクトが目を輝かせて尋ねてくる
こういう所は 外見相応に見えるのにと苦笑する
チケットに印刷されている船乗り場と船名を探し 指し示す
「あれだ」
「おっきい!」
「あれ位じゃないと 航海できんだろ」
一応旅船なんだし と付け加える
東の国へ届けるのだろう 荷物も積み込まれている
里帰りなのか はたまた旅行なのか 様々な姿の人が船へと上がっていく
出向時間はまだまだ先だった あと二時間はある
ファンドとティクトは船を見てはしゃいでいるし まだ乗るにしても早い気がした
(もう一度荷物確認したほうがいいか?)
必要な物は揃っていると思う
だけど 用心することに相違ない
数日間は海の上なのだ 何かあれば対応するにも限度がある
船にはそれなりの設備も整っているとは思うが 何か拭えない予感がするのも確かだ
幸い 懐はそれなりに充実はしている
最近の一番高い買い物は他ならぬ この船のチケットだ
それでもまだゆとりがある分 何か買い足せるような気もする
「夜志露 どうしたの?」
「いや 何か買い忘れてないかって」
「じゅうぶんあるよ?荷物は」
「ああ それなら いいんだけど…」
自分でも思う程 歯切れが悪い
双子が同じように 同じタイミングで眉をしかめる
さっきからしている何ともいえないこの予感は 胸騒ぎは何だろう
ざわざわと本能が告げるかのようで
ここにいてはいけないような気がした
― 探さなければ 見つけなくては ―
「夜志露!」
気付けば荷物を双子に預けて駆け出していた
ファンドの声が後から聞こえる 切羽詰った声が
「間に合うように帰る!」
「やしろっ!」
「危ない奴についてくな!?」
「わかってる!!」
ティクトが怒ったように反論して 不安げにこちらを見ていた
港から離れていくにしたがって それは確かなものに変わりつつあった
土地勘はほとんど無いのに 迷い無く道を駆け抜け 角を曲がっていく
息が軽く上がった後にたどり着いたのは 港が一望できる小高い丘
寂れたような まるで廃墟のような教会らしき建物が ぽつりと建っている
辺りには人がいない
まるで忘れ去られたかのように ここだけがポツリと存在しているかのように
一歩一歩 確かめるように教会へと近づく
教会は丘の端に建っていた なので教会の裏は 自然に切り立っている崖となっている
自分が草を踏む音以外 耳に届かない
街の喧騒すら 風に乗って届いてこない
緩やかに教会を見上げれば 教会と一緒に真っ青な空が広がっているのが目に映る
ただそれだけで 錆と青々とした蔦に絡まれた教会が 一層その存在感を増してくる
(確かに ここだ)
告げていた場所はここなのだと 再認識する
その証拠が 何者にも干渉されることなく ココに佇んでいる事
開けている土地なのに何故誰もいないのか 考えれば直ぐにわかることだった
一時的ではあるが 消されているのだ この場所だけ
広範囲にまでその影響を及ぼすことが出来るのは 一人しか俺は知らない
もう一度 緩やかに教会へと視線を上げた
頭上と言っても過言ではない その教会の鐘のある塔を
「来たか」
低い 声が耳に届いた
ずっと追いかけて 探している"彼"がそこに佇んでいた
「時間が無いんだ 手短に頼むよ ソウマ」
「そうだな 夜志露」
そう言って"彼"が軽く屋根を蹴った
14.頭上には真っ青な空とあの人が
→戻る
背景の元絵