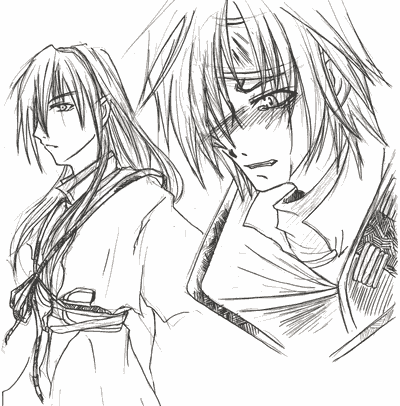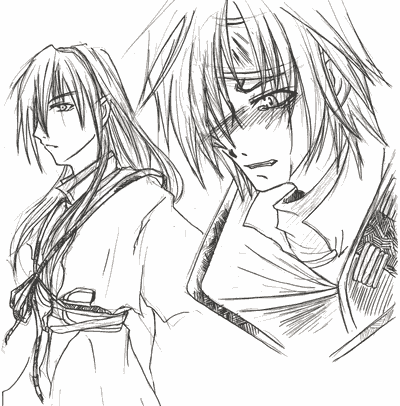
海が 好きだった
正確にいうなれば 海に囲まれたこの国が好きだ
過去形じゃない 現在進行形
風が磯の香りを運んで 海には様々な船が行き来する
五洲亜 −イスア−
それがこの国の名前
それを聞くたびに ひどく懐かしく思う
「キオウ なに耽ってんだ?」
ジンが不思議そうに尋ねる
書庫の整理を任された彼は 朝からずっと書庫で作業をしている
独特のにおいが鼻につく
入り口を開けて 換気をしようにも書庫にあるのは小さな窓
十分な換気をするには随分と時間がかかりそうだ
「珍しい?」
「いや たまに耽ってるだろ」
そういってジンは作業を再開する
虫干しもかねて書庫に詰まれた本や巻物を廊下に並べていく
今ようやく半分ほどが整理し終えたぐらいだ
バサリと派手な音を立ててジンが固まる
足元には散乱した本と巻物が転がっている
どうやら 一冊抜いたらおまけで落ちてきたらしい
「破れてないよな」
恐る恐るジンが拾い上げていく
「破れてたらどうすんの?」
「……ここ一番古い文献の棚だぞ」
「…一番 古い って」
脳裏をよぎったのは”国宝級”という三文字
それがわかったのか いささか緊張を解いてジンが言う
「重要なのは別の場所へ厳重に保管されてるからいいものの」
「わージンなげやり」
「手伝えよ」
「はいはい」
丁寧にかつ素早くという 割と無理な注文付ときた
ジンに持たせるように拾い上げていくと 一冊の本が目に留まる
自分よりは一回り小さいが 今の自分は人形ほどの大きさだ
じっと手にとって見ていると ジンがヒョイと抜き取る
自分の目の高さまでもっていき 最後のページを捲る
「『創立記録』だ」
「『創立記録』? なんの」
「この国の」
ジンが昼休憩に向かったのを見送って パラパラと頁を捲っていく
書庫の中は ひんやりとして少々肌寒かったが 気にしない
それに 一般の人に自分の姿は見えないのだ
ある程度の修練を積んだ人や 霊感とかそんなチカラがある人には見える
だから 傍から見れば 本のページが勝手に捲られていく という形に最悪はなる
こんなところで怪談を増やしたくはないし 直射日光下での読書は目によくない
ので 人目につかない書庫の中は最適となる
「そうりつ…かー 普通は建国じゃないのか こういう場合って」
仮にも一国なんだし と独り言が漏れる
懐かしいと思う反面 こんな事があったのかとも思う
自分も忘れている事がたくさんあるのだと 改めて気付かされる
それと同時に−
「きっと もう 忘れ去られてるんだろうな」
自嘲してしまう
何も求めず ただ駆け抜けていったあの頃が やけに懐かしい
馬を駆けさせ 船を出して 剣を振るって
傷つきながら 血に塗れながらも あの頃は充実していた
疲れても 追い立てられても 攻め立てられながらも 自身は懸命に生き抜いていた
そんな頃があった
「悠長だな」
反射的に顔を上げると 日に透けた緋色の髪が目に入る
自分の髪とは 反対の色
逆光でその表情はわからない
「ツァン」
同じような 人形ぐらいの背丈で 宙に浮いている
ふわりと 書庫に入ったとたん その姿は一変した
緋色の髪が 緩やかに揺れると同時に術師のような風貌をした彼が立っていた
赤い中に蒼い色の紐がやけに映える
「本 燃やすなよ?大切なんだから」
ポツリと呟く
「お前は”水”だろう 丁度いい」
「そりゃそうだ」
嘆息して 同じように姿を変える
変えるといっても こちらが本来の姿といっても過言ではない
今でも鎧を身に纏うのは 未練がましいのか
若葉色の鎧は あの頃の自分が纏っていたものだ
彼と同じ しかし対色の紐が揺れる 彼が蒼なら自身は紅
額当てとして巻いている布は 海のような空のようなアオ色
それが 視界の隅で揺れる
「で?なんでわざわざ」
「懐かしいにおいがした それだけ」
「なんだよ それ」
音もなくスルリと書庫内を行けば 何もない壁に手をつく
「お前の方が鼻がきくだろ 犬」
「結構麻痺してるが」
「使えん」
「うるせ 埃と墨と紙は結構におうんだよ」
「ここにあった」
壁に手をつけたまま 視線もそのままに 突然話の流れが変わる
そういうのも あまり気にしてないのが彼だ
それに比べて 自分はまだ人間くさいんだろうか
幾分表情に懐かしさが浮かんでいる点では 彼も同じように思えるが
彼が何を考え 何を感じたのかは 自分にはわからない
「何が?」
「ここにあったのは確かだ」
注意して嗅げば 常人よりも発達した嗅覚がそれを嗅ぎ分ける
そして
ふと脳裏を過ぎったのは あの時の事だ
始めて”主”に会った時
あの時の記憶は 普段なら奥底にしまってある筈なのに
こういう時 不意をついたようにその存在を主張し始める
「お前のものだったんだろう?」
うっすらと よくよくみれば後がある
横に細長い影
彼が何を言っているのか 理解した瞬間 崩れそうになった
「ああ 元は…な」
自分が愛用していた太刀がそこに掛けられていた
それすら 忘れ去りつつあった
そっと その部分に触れれば溢れてくるものは あの頃の記憶
際限なく それこそ抑制が聞かぬほどに それらの記憶は蘇ってくる
―お前が大きくなったらこの太刀をやろう
―ほんと?じいさま!?
―ああ
幼い童を膝に乗せて そう約束した
それまでに この戦を終わらせて・と必死だった
海上戦の最中 最後の大戦で 自身は終わったのだと
あの童に 己の孫に 約束をしたのに・と
陽の光が揺らめく水面に 思わず手を伸ばし 霞んでいく意識を手放した
ごめんな と
一言も伝えられずに 勝手に海へ帰る自身を呪った
何もしてやれなくて ごめんな と
終わらせられなくて すまなかった と
後悔と自責の念が己に纏わりついて 足掻くことすら出来ずに
「思い出させんな」
「事実を 述べただけだ」
ぱたぱたと 足元に小さなしみが出来ていく
気付けば視界は滲んでいて 嗚咽が漏れていた
壁にすがり付くように 懇願するように 額をこすり付ける
全てを消え去る事として 忘れ去られる事として納得させていたのは
他ならぬ己自身だったのだ・と
どんなに思っても あの頃に戻る術はなく
ただただ あの頃を共にした彼らに 想いを馳せた
行く末を見る事を ある種の諦めだと思った
それでも 彼らは懸命に己の志を継いでくれていたのだ
「ここは この建物の中でも特に 古いらしい」
「そう か」
「ああ この辺は建設当初からさほど変わってないらしい」
「え」
そう告げたツァンは ふらりと書庫の入り口へと向かった
先ほどと同じように姿を一瞬で変えると 人形ほどの大きさになった
気だるげな目でこちらを一瞥した後 書庫を後にする
「ヒノトの休憩が終わった」
そう一言だけ告げて
ヒノトはジンとは同僚にあたるし 同じ組の”組方”でもある
休憩が終わったというなら ジンもそろそろ戻ってくるだろう
ゆらりと姿を消したツァンを 何となしに見送った
「キオウ どうした?」
「…を?」
いつの間にか入り口には 訝しげに眉を寄せているジンが立っていた
そういえば姿を変えたままだったと 気付く
誤魔化すように笑いつつ いつもの姿に戻れば 彼はそれ以上追及してこなかった
「なあ ジン」
「なんだ?」
外に干してあった本と巻物を抱えつつ ジンが作業を再開している
ようやく最後の棚に差し掛かり 終わりが見えてきた頃だ
「ここって 古いのか?」
先ほどツァンが口にしていた事が気になって尋ねる
作業を継続させながら ジンが少々考えた後に口を開いた
「古いぞ」
「どれくらい?」
「初代から」
「は?」
「初代がここを建てたときから ほとんど手を加えてない筈だ」
「そ れってすげえことじゃ…」
「気にしてたらキリがない」
そう言われればそうだ
この近辺の建物は 確かそんなものがほとんどだったような
形をなるべく変えないように補修・補強が行われているとか いないとか
「太刀が あったそうだ」
「は?」
ジンが指した先は 先ほど己がすがって泣いた箇所だ
「初代がここに太刀をおいてた 今は違うところにあるけど」
行事ごとに確か 奉納という形で日の目を見てる筈だと ジンが言う
実践的なものはないが 手入れは行き届いているとも
「古い太刀だけど 大切にちゃんと伝わってる」
初代もそう言い残したらしい
作業を黙々とこなしていきながらも ジンはそう教えてくれた
自分が離れている間に 随分と様変わりしたように思えたが
根底は あまり変わっていないのかもしれない
「意外と 人間もすごいだろ?」
どこか満足げに言うジンが 書庫の入り口に立っていた
ちょっと 本当にちょっとだけ 孫に似ていたような気がした
「ああ そうだな」
”志”は 受け継がれているのだろうと 信じて
17.消え去り忘れ去られつつ
→戻る
背景の元絵