声がする。
今は確か寝ている状態の筈だ。
深遠から静かに自分を呼んでいるように思える。
瞼は落ちているが、自分が何処に居るか何となくぼんやりとわかる。
たゆたうような水面に浮かんでいるような感覚。
母親の腹の中に居る時、羊水に浮かんでいる時はこんな感覚だったのだろうか。
居心地がいい。
反面、ここに居てはいけない気がする。
― …… ………
何で呼ぶ。
何で呼ぶんだ。
いつの間にか右手に何かを握っている感覚がある。
それは慣れ親しんだ感覚に近い。
ただ、あまりなじみの無い感覚に近い。
そして…左肩に熱を感じている。
―何故だろうか。
考えるほどの余裕を持ち合わせているにも関わらず、意識は覚醒しない。
ぼんやりとした感覚で目覚めるのが、最近恒例になりつつあった。
そしてそのぼんやりとした中で覚えているのは…
* * * * * * * *
楠総学園がその壮大な敷地に生徒達を収めていく。
入学式から三週間程が過ぎた。
クラスも馴染み始め、部活も徐々に活気を取り戻し始めた頃である。
近隣でも有数の進学校と謳われるこの学園は、施設も一通り揃い充実した学園生活と自己の自立を掲げていた。
それを証明するかのように、卒業生は有名どころの大学へ進学および就職をしている。
楠総学園は中等部・高等部からなる。
その高等部から三つの学科―特進科・普通科・体育科―に分かれる。
そして、その特徴として名高いのが、学生寮。
高等部では完寮制であるため、学生寮の棟が幾つか学園周辺に建っている。
学生はそこで一人暮し同然の生活をしているのだ。
これも、学園でいう「自己の自立」に繋がるらしい。
そんな一風変わった学園へ入学したいと願う者は少なくないらしい。
窓際の一番後ろ、という絶好の位置で戌塚志乃弥はぼんやりと窓の外を見ていた。
体育科のクラスは一クラスしかなく、割とほとんどの者が打ち解けられている。
担任の意向により、入学式がすんだ後に、席替えが行われた。
その結果、戌塚は窓際の一番後ろという絶好な場所を得たのだ。
前の席は江山新、隣は井川総騎。
斜め前には犬飼夜樹に、井川の隣は大都蓮璃である。
周りは部活について盛り上がっていた。
入る部を決めた者、まだ迷っている者…様々だが体育科ともあって、部活面は活発だそうだ。
「戌塚、ここ最近寝不足そうだな」
隣にいる井川が声をかける。
気付けばいつも野菜ジュースを啜っている・というのが井川である。
毎日毎日啜っているので入手先を尋ねれば「企業秘密」と返されたぐらいだ。
井川の近くには犬飼と江山と大都もいる。
クラスでよく一緒に居るメンバーである。戌塚もここに入っていた。
「…そうかもしれない」
「かなりあやふやだなぁ」
「寝ているには寝てるんだが…寝た気がしない・というか」
「微妙なとこなんだな」

500mlはあるだろう、紙パックの野菜ジュースを啜りながら井川が言う。
犬飼も同じ様な反応を示している。
この井川・犬飼の二人は、昔からの付き合いらしい。
阿吽の呼吸というのか、クラスでも名物になりつつあるムードメーカーのような存在。
その二人が突っ走りすぎた時に、戌塚が止めるという公式が出来つつあるのが現状である。
「倒れる前にちゃんと保健室行くのよ?気分悪くなったらすぐ言って」
「……人が、」
「それは我慢して」
近くに居た大都が戌塚に言う。
面倒見が良いのか、姉御肌なのか、戌塚にとって大都の心配は嫌ではない。
共に剣道部へ所属する事が決まっており、中学時代ではライバルだった。
ライバル兼親友という関係だろう。
幼少から剣道をしている戌塚にとって、大都はよき理解者であり、相談相手であった。
その大都が同じ高校を受けると知らず、入試時に始めて知った。
戌塚が重度の人酔いの性分・というのはすでにクラス全員が認知している事である。
学生集会等、高等部の人数が一斉に一箇所所へ集まる、と言った時の戌塚は…それこそ見ていて危なっかしいものがあったのだ。
顔面蒼白・千鳥足・覇気が無い…などなど好き勝手に言われている割には結構心配されている。
集会等では出席番号順に並ぶが、戌塚はクラスの行為により一番後ろへとその位置を移動させている。
人情味が溢れるな・と戌塚自身感謝し尽くせない。
「クラスの人数は大丈夫だ、慣れてきた」
「週五日も顔合わせばねー…そりゃ慣れるわよ」
「次は頑張って学年集会に慣れないとね」
ほんわかした雰囲気を纏いながら江山が口を開く。
小柄な体をしているが、弓道の腕は確かなようですでに弓道部へ入る事が決まっている。
入試時にそういって決まっている者が半数はいるのだ。
好きだからまあいいか。
それが戌塚の見解であり、基本である。
「そういえば、何を話していたんだ?」
「あー…そろそろ実力テストの結果が出る頃だね〜って」
どこか遠い目をしながら大都が告げる。
それを耳にした瞬間、井川と犬飼がこの世の終わりとも言えるかのような表情となり、沈んだ。
最近のぼんやりとした感覚が大半を占めていたので、思い出すには多少時間を要した。
そういえば、入学してすぐ辺りにテストがあったような気がする…。
学年共通らしく、上位二十位までに入れば生活費が支給されるとか、そんな特典があった筈だ。
少しでも生活費を抑えたいが為に、いつも以上に勉強したような気がする。
それもここ最近のあの"夢"のせいで薄れてしまっていたのだろうか。
記憶が薄れてしまったのか、遠い事のように認識してしまっている。
しかし、その上位二十位へ入るには随分と不利な点が多い。
その不利な点として真っ先にあげられるのが―
「上位は特進科が占めるんじゃないのか?」
特進科。名の如く進学へと特化した学科であり、この学園の平均偏差値を底上げしている科でもある。
そして次に普通科。この普通科も徐々に理系文系と分かれて行くのだ。
偏差値の幅は広いが特進科でも通じる者が毎年数人はいるらしい。
体育科はどちらかと言えば運動方面へと重点を置いているので、勉学の面では多少なりとも劣る。
劣るが―内容としては普通科と平行・らしい。体育科からでも時折上位に入る者もいるそうだ。
だがそれは随分と稀なケースではある。
戌塚自身、その稀なケースに入って支給を受けたい・と思う反面、目立ちたくないという思いもある。
元来そのような事へ執着する性質ではないのだ。
己のやりたいように、気の済むまで、周りに迷惑がかからない程度に実行する。
それが、戌塚の根本的な性質であり、ささやかな願いでもある。
「でしょーねぇ。月一万の生活費支給はおいしいんだけどな」
次のテストまで、つまり中間テストまでそれは継続し、そこで新たに上位二十名が決まる。
常に支給を受けたければその都度上位に入らなければならないのだ。
その特典のお陰か、毎回生徒側のやる気が高いらしい。
結果、進学校というのは伊達ではない程の学校平均偏差値を叩き出す。
あまりまわらない頭をよそに、戌塚はぼんやりと視線を窓の外に移した。
遅咲きか、それとも違うのか、桜色がまだ正門までの街道を彩っている。
クラスの喧騒が遠巻きに聞こえる。
そういえば、自分はどんな"夢"を見ていたんだっけ。
閉じかけた瞼へ一応は抵抗してるが、その抵抗も長くは続きそうに無い。
いっその事、このまま睡魔に従ってしまおうか、と戌塚は思案する。
"夢"の再来を願おうか。
ざわつきがより一層、遠く感じられるようになる。
意識的に遠のけられるようになれば随分と楽なものを・と頭の隅の方で思っている。
切り取られた世界を感覚的に察知しながら、戌塚は徐々に意識を落していった。
―…来た? 来た?
ぼんやりとした意識の中、遠巻きに聞こえる喧騒よりも鮮やかな声。
全ての音を抑えた上で、鮮明に届く。
耳で聞く・というよりは、本能的に拾い取る・と言った方が正しいかもしれない。
何処かで聞いた事がある。
そういえば、最近ずっとこの声を聞いていたような気もする。
でも今は眠いのだ。
このまま寝れば、ホームルームも寝過ごす事決定だろう。
だが仕方ない。眠いのだ。寝させてくれ。
戌塚はそう願うが、意識の何処かでは起きようとしている。
このままではいけない・潜在的なものが何かを告げる。
だが、眠い。
―後にしてくれ…
ほぼ反射的にそう答えると、戌塚は睡魔に誘われる様に、素直に寝た。
戌塚が覚醒するのは、その十五分後。
担任の教師によって丸められたプリントで軽く叩かれてから・である。
スパン・と小気味良い音を教室中に響かせ、尚且つ一呼吸ほど間を空けてから戌塚が起きる。
起きるといっても、寝ぼけ眼で状況を全く理解していない状態だ。
さっき何か音がしたな。何故担任の先生がここにいるのか。
何故クラスメイト全員がこちらを見ているのか。
戌塚には全く理解できていない。理解出来るほどのレベルまで意識はまだ覚醒していない。
ただ一つハッキリしているのは、多少、寝不足が解消されたという事だけである。
ジャージを着ている担任―確かサッカー部の顧問とか言っていたな―が肩を落してこちらを見ている。
その姿を見てようやく、自分が起こされたのだ・と理解した。
「…起きたか、戌塚」
「……一応」
軽く叩かれたのだろう、多少違和感を覚える頭をさすりつつ視界に入る範囲で周囲を見る。
視界の隅に映っていた隣の席の井川と目が合う。
よほど珍しかったのか、ぽかんとしたままこちらを見ていた。
その手には、意識が落ちる前に見た野菜ジュースのパックは無かった。
いつもホームルーム前には飲み終わっていたな・と思い返す。
ようやくその辺りのレベルまで覚醒し始めた。
「聞いていたか?俺の話を」
「いえ、全く」
「…その潔さは心地良いな」
「…………あり、がとう…ございます?」
少々しょんぼりとした後姿で、担任が教卓へと戻って行く。
ああ、確か新任三年目・とか初日に言っていたような気がする。
心の隅で担任に謝りつつ、視線を窓の外へ移動させ、すぐに担任へと移する。
外を見るというのは反射的な行動に近い。戌塚が気持ちの切り替え等でよくやる行動でもある。
一体何の話をしていたのだろうか。
ホームルームが終わった後にでも聞いてみよう。前に居る江山辺りに。
今だ完全に覚醒しているわけではないので、予想もたてられないが…。
担任が連絡事項を二〜三告げている。
「最後に…戌塚、江山。昼休憩、十二時半に学長室へ来い」
遅れるなよ、と付け加えられた。
突如呼ばれる自分の名前。
さらに、学長室へという点で一体なにかしたか?と反射的に考えてしまうが、思い当たる節は無い。
自分が思い当たらないだけで、何かしたのだろうか・とも考えるが、思いつかない。
わからないものわからないので後で考える事にしよう。一旦思考を切り取った。
「じゃあ、以上だ」
授業に遅れるなよー、と告げると担任は教室を後にする。
それと同時に教室は再びざわめき始める。
一時間目は確か古典だったな…と思いながら、戌塚は学長室はどこだったか考える。
入学式の次の日ぐらいに、校内の案内を受けたがそこまで覚えていない。
必要な個所以外、ほとんど覚えていないというのが、現状だ。
大体、初日に一挙に校内を案内されても覚えきれるわけないだろ・と毒づいたのを思い出す。
教室に張り出されている「校内地図」にも、学年棟と特別教室ぐらいしか載っていない。
詳細は中庭にでかでかと建っている「校内見取図」で確認するしかないか。
そのような状態なのに、何故いきなり「学長室へ来い」とはどういうことだろうか。
「校内見取図」が無ければ、この、ただでさえ広い校内をさ迷い歩けという事だろうか。
後でその見取図の建っている"中庭"を確認しなければ…。
広大な敷地内には"中庭"と称される箇所は三〜四箇所あるというのに。
「志乃弥?」
不意に呼ばれて我に返る。
反射的に視点を上げれば江山がこちらを見ている。
呼んだのも江山らしい。
小首をかしげて不思議そうにこちらを見ていた。
「…なんだ?新」
「いや、何考えてるんだろうって」
手を当てながら眉間に皺寄ってたよ、と自身の眉間を指しながら言う。
そう指摘されて言葉に詰まった。
高校へ入ってから発覚した癖である。何か考え込んでいると額に手を当て、徐々に眉間へ皺が寄っていくらしい。
小中学校で発覚しなかったのは、恐らく考え込む・という行為自体を人前でやらなかったからだろう。
家にいても、家族からなんとも言われなかったので、あまり気付かれていないのかもしれない。
一癖も二癖もある家族を思い出して、少し懐かしくなった。
「また、か」
「志乃弥は割とそういう時顔に出やすいね」
「みたいだな…」
危ない危ない・と気持ちほど眉間を伸ばしてみる。
江山が苦笑しているが、このまま皺を刻みたくも無いのでしばし続けた。
視界の端に教室の前の壁、黒板の上にかけてある時計が目に入る。
一時間目が始まるまで…あと五分か。
「ホームルームは何か言ってたか?」
「ううん、そう重要そうな事は…最後のぐらいしかなかったと思う」
「学長室…か」
「何かした、かなぁ」
「身に覚えは無いんだが」
「私もよ?」
「そもそも、学長室はどこだ?」
「さぁ?」
教室のざわめきが、多少変わった。
見れば古典の教師が既に教室に入ってきている。
まだチャイム鳴ってないんだがなあ、と戌塚がこっそりと思う。
何度か授業を受けて、現時点で分かった事もある。
授業開始はチャイムと同時であり、授業終了は五分オーバー・という事だ。
唯一の救いが、次の時間、つまり二時間目が同じ教室・という事だけだろう。
教師が来た。
それにより、教室は渋々ながらも授業体制を取らざるを得ない状況に移った。
淡々と進んで行く授業と平行して、戌塚は"夢"を思い出していた。
ホームルーム前、確かに「来た?」と聞こえた。
クラスの誰の声でもない"声"。
女子特有だろう、少々高めの、どこか華があるような声。
まるで待ちわびていたかのような響きでもあった。
―後にしてくれ
そう言うと、すんなりとその声は引いて行った気がする。
教師が板書を始めたので、ノート、および教科書へ書いていく。
来週、小テストを実施する・と宣言したのを思い出した。
二〜三回に一回は小テストするらしい。
他人事のようによくするな、と感じる以外何もない。
勉強という事に対して、それ程執着心もなく、どこか事務的なものを感じているのかもしれない。
思えば、全般的にそれ程"執着心"というものが無い気もする。
好きな事・そうでないもの、との差がハッキリとしているとも友人達に言われたような。
「何だ、井川」
「……え、あー」
不意に視線を感じ、隣を見れば井川がこちらを見ていた。
そもそも教師に見つからないように・という前提を置かなければならないのが授業中だが。
幸い教師は板書の方で手一杯のようだ。
かといって油断していると、こちらが取り遅れる。
この教師は板書をした後、一通り説明した後、綺麗に消すからだ。
遅れないように、説明を聞き漏らさないようにと生徒側もかなり必死である。
それが五十分間続く。
これは現代で繰り広げられる、教師対生徒の静かな攻防戦だ。
主導権は教師にあるが、質問という反撃の措置は生徒側にある。
古典ではあまり使われていない措置ではあるが。
思いあぐねいている井川が再び口を開く。
「……ノート、後で貸してくんない?」
ちらり、と井川が自身のノートを見せる。
もの見事に―取り損ねたようで、ほぼ白紙に近い状態のノートが戌塚の目に入る。
古典でノートを取り損ねると言う事は、自殺行為に等しい。
小テストはこの板書された範囲から出される。
無論、教科書からも範囲として出るが、内容を占める率は板書された方が、教科書を凌ぐ。
成績に反映させる・と既に教師が宣告しているのだ。手を抜けるはずが無い。
手を抜く以前に、気が抜けないのが古典の授業なのだが…。
井川自身、かなり痛手を被っているっているのが、表情と雰囲気からよくわかる。
「…いいが、」
「ホントか!」
先程までの表情が、がらりと変わる。
感情をそのまま出すのが井川だ。
あまり感情を表に出さない戌塚とは逆のタイプだが、馬が合うのか、衝突と言う事はまだ無い。
浮かれる井川に、戌塚が忠告とも言える一言を放つ。
「多分…次、当たるぞ」
授業中で・だろう。
古典の教師に限らず各教科の教師によくある事で、何の前触れも無く生徒へ問題を投げかける、あれである。
ご指名、という生徒側からすれば、遠慮したい授業中のイベントである。
それをクリアできるならばいいが、大半は周りの協力が無ければクリア出来ない。
そういう風に、教師も考えていれば、ただ単に思いついて・という事もある。
思いつきの場合は、和やかなままに進むのだが、如何せん、古典の場合はほぼ吊るし上げ状態なのだ。
答えられなければもれなくお小言が三分前後ついてくる。
その間、ずっと立っていなければならない・というのも、辛い状況を作り上げる要因の一つだが。
「…ま、ぢで?」
「多分な。出るとすれば…」
戌塚が打開策を井川に手早く伝える。
井川は、必死になって一字一句逃さぬように頭に叩き込み、ノートへ書きなぐる。
多分・という域ではあるが、井川は何度かその戌塚の勘に助けられている。
天性なものなのか、戌塚はそういう事に関して鋭かった。
観察力があるのか、洞察力なのか、本人ですらわかっていない。
根拠は無いが、結果を見ると九割は当たっている。
信じないよりも信じた方が助かる率が高いのだ。
こんな時に吊るし上げなんぞくらうものか・と井川も必死である。
一通り、戌塚が伝え終え、井川がそれを見直した。
「井川」
不意に教師に名前を呼ばれた。
呼ばれた井川は、ビクリと体を震わせた後、反射的に返事をする。
「教科書二十三ページ、三段落目を訳せ」
「え、あ…はい」
毎回、このように唐突に当てられては現代語訳を読ませるわけで。
古典では予習という、回避行動が避けられない。
避けられない上に、さらに突っ込んだ質問も来るので、各単語の意味等も調べていなければ万全とは言いがたい。
古典のある前日では、そういった対応も兼ねて、クラス一丸となって予習の見直し等がされる事もしばしばある。
その時、あてにされるのが古典の得意な者達である。
筆頭に上げられるのが、戌塚と前に座っている江山の二名。次いで井川の隣に居る大都である。
他に数名いるが、特に頼られているのはこの三名。
この三人から遠いクラスメイト達は、モールス信号でも本気で習得してやろうか・と思わせたほどである。
それ程に、古典という教科は…強敵なのだ。
井川が戸惑いながらも、指定された箇所の訳を答える。
教師の表情は変わらず険しいままだが、一応満足したのか、井川を座らせた。
「では次…戌塚、訳せ」
「…はい」
短く、気付かれないように嘆息して戌塚が次の段落を訳す。
すらすらと訳を答えていく姿は、井川に比べて様になっているように思える。
隣にいる井川は思わず、戌塚を見上げていた。見上げると言っても、視線を上げるだけだが…。
周りに気付かれないように・という前提があるからだ。
カリカリと、ノートを取る音、教科書へ書きこむ音が耳に届くが、井川はそれらを実行はしていなかった。
ただ、戌塚を見上げていた。
「…割と、訳しているな」
その教師にしては誉め言葉を貰って、戌塚は席についた。
表情は、多少疲労が見え隠れするが、すぐに治るだろう。
教師が再び板書をする為に、黒板を綺麗に消し始める。
ここで私語なぞすれば、時間いっぱい標的にされる事をクラスは身をもって知っている。
わかっている罠へ、かかりに行きたくは無い。
そういった暗黙の了解のもと、古典の授業は刻々と消化されていった。
その後、これといった事も無く時間は過ぎ、珍しくチャイムと同時に授業は終了した。
教師が教室を後にするまで、気は抜けなかったが、休憩時間の半ばとなればクラスはいつものように賑わい始めた。
* * * * *
四時間目の授業も無事に済み、昼休憩へと入る。
食堂利用者がほとんどではあるが、稀に自身で弁当を作ってくる者もおり、さらに先にパン等を買ってくるという学生もいる。
昼休憩は高等部共通の時間であり、食堂しかり、売店しかり…昼は戦場さながらの状況なのだ。
重度の人酔いを持っている戌塚は近づきたくない一角である。
なので、戌塚は自作の弁当を持参する・という行為を続けている。
体育科は普通科・特進科に比べて体を動かす授業が多い。腹が減るのも早ければ、食べる量も多い。
一緒に食べている江山・大都も同学年の女子に比べれば大きめの弁当箱を広げている。
「にしても、志乃弥よく食べるわね…」
それでも戌塚に比べれば小さい方だ。
二段式になっている弁当には、下段はご飯、上段にはおかずという組み合わせになっている。
男子用でも通じそうなその量を戌塚は見ていて清々しいほどの速さで食していく。
特に早いわけでもなく、遅いわけでもなく…テンポ良く箸が進んで行く。
「そうか?」
「まーここは食べてないとやれないしねえ」
「お腹空いたら部活まで持たないよ」
「まぁ、そうだな」
そんな調子で三名が食していると、ガラリと勢い良く教室のドアが開いた。
両手にパンやおむすびを抱えて多少ボロボロになりつつ入ってきたのは井川と犬飼だ。
その二人が教室に入ってくるや否や、あちらこちらから声がかかる。
「俺の頼んだのあったかー?!」
「それそれ!!」
「一個売ってくれよ!」
「ちゃんと全部取れたから落ち着け!!」
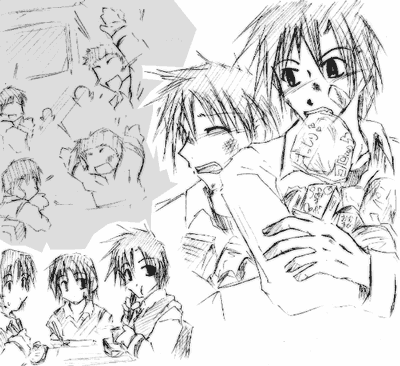
犬飼が叫びながらパンをぽんぽん投げていく。
投げられたパンは頼んだ主であろう元へ、寸部の狂いも無く届けられた。
代金前払いで代行して買いに行く、という二人のこの光景は既に日常茶飯事となっている。
あの人ごみの中をするすると進んで行き、目当ての物を手早く買って行くのだ。
慣れというよりも、一種の才能じゃないのかとも思わせる。
その二人が全て配り終えたのか、こちらに歩いてくる。
いつものように、いつもの席へ腰を下ろす。
「お疲れ」
「「うん」」
戌塚が声をかけて、井川・犬飼が答えて、この日常茶飯事は一応幕を閉じる。
この五名で昼ご飯を食べるのが、いつの間にか恒例となっている。
「今日も大盛況ね〜、儲かってんの?」
「まさかー。でもたまに奢ってくれるな」
大都が笑いながら言えば、犬飼が笑いながら返す。
二人に買い出しを頼む者は、たまに奢ってくれるらしい。
パン一個やジュース一本。そんなものだが、嬉しいものは嬉しい。
好意は素直に受け取る事にしている、井川と犬飼はそういう性格なのだ。
二人だから許される・というのもある。ムードメーカーという肩書きは伊達ではないようだ。
「戌塚ー俺のめしー」
「……ああ、」
井川にせがまれて戌塚が鞄から取り出したのは、ラップに包まれたおにぎりだ。
市販の物より一回り大きいものが、二つ。
そして井川が変わりに出したのは、ヨーグルト。
売店でも売れ筋の商品で、昼休憩が開始して十分前後で売りきれとなる。
入手はかなり困難な部類に入る。
「これでいい?」
「あー…悪かったな」
「いいよ、米があるだけで腹持ちが違うんだから」
さも当然と言った物々交換だが、三名は思わず箸が止まった。
犬飼に至っては勢いあまってパンの袋が盛大に裂けている。
「……あんた等、いつの間にそんな」
「取り引きしだしたんだよ…」
「おっきいね、そのおむすび」
「新!そこツッこむとこ違う!」
大都が思わず突っ込むが、江山だけはおむすびに目が行ったようだ。
たしかに、大きい事には大きい。軽く手を握った大きさに近いのだ。
「え、だって蓮璃…おっきいよ?ご飯二杯分っぽい」
「……やけに詳しい見解が」
「まぁ、それぐらいだな」
「しかも当たってる!」
「わーい!」
昼休憩にはこのようなやりとりが繰り広げられる。
この五名、クラスでは暗黙の了解となっているが…名物になりかけているのだ。
昼に流れるテレビ番組のような光景を楽しみつつ、クラスメイトは昼食を平らげていく。
徐々に昼食を終わらせていく者が増えて行くのと比例して、校庭も賑わい始める。
授業での鬱憤を晴らすかのように、生徒達―主に男子生徒―が体を動かすのだ。
サッカー、野球に始まり、バスケなどが校庭のあちらこちらで繰り広げられる。
その時間帯に映り始めて、ようやく戌塚と江山が動き始める。
いつもよりも早いペースで食べれば、丁度よい時間帯にはなっただろう。
時計は十二時十五分を指した所だった。
「蓮璃、学長室って…どこだ?」
戌塚は兼ねてからの質問を大都に向けて見る。
ペットボトルの飲料を飲みつつ、大都が思案して、
「ああ、中庭にある"校内見取図"の場所ね」
全てを言わずとも、大都にはわかったらしい。
学長室が分からなければ、校内見取図で確認するしかないのだ。
「暇だし、一緒に行ったげる」
「ホントに?いいの?蓮璃」
「いいわよ。志乃弥と新だけじゃ心細いし」
確実に戌塚が人酔いを起こすであろう・という予測の元で大都が同行を表示する。
江山だけでは、恐らく人酔いを起こした戌塚を連れて行けないだろう。
中学時代からの友人・という事で戌塚の扱いには大都の方が長けているのだ。
高校時からでは、まだ慣れていないのでどうすればいいか、江山はまだよくわかっていない。
"扱い"といっても人ごみからふらりと逃げるような戌塚を、しっかりと捕まえて連れて行くだけなのだが…。
「じゃー俺も行くー」
「俺もー」
「なんで…」
「「暇」」
双子のようにぴったりと合った声で井川と犬飼が言う。
実際、この二人は生き別れた双子じゃないのか・という憶測が飛び交うが、一応他人のようである。
外見も割と似ているし、何より全てにおいて息が合っているのだ。
その気になれば、二人共入れ替われるような気がする。
朝のホームルームで担任から言い渡された「学長室に来い」という不可思議なもの。
いつの間にか、人数が増えてしまっている…。
→次へ